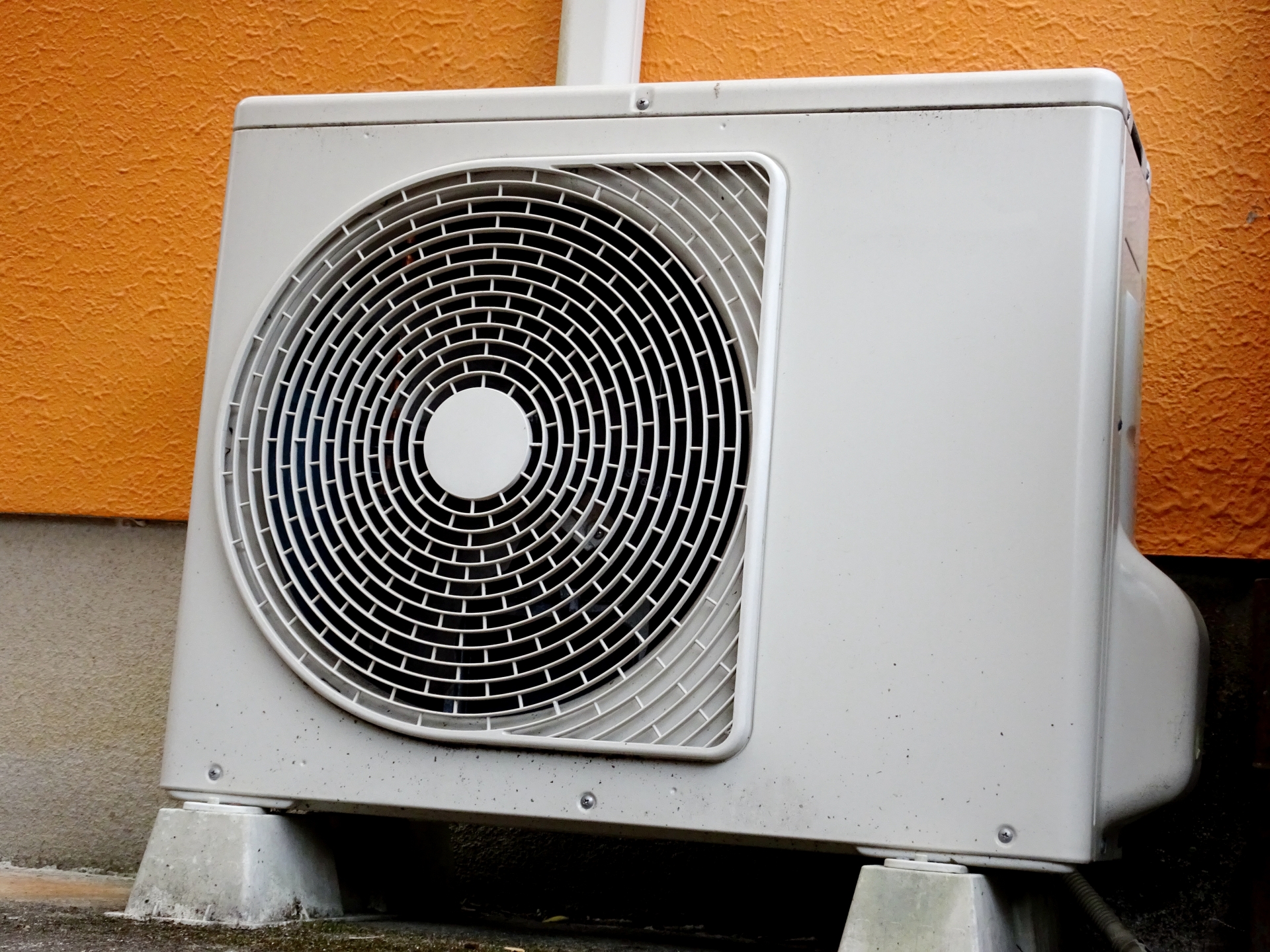高齢者の一人暮らしは防犯対策が重要です。
この記事では、在宅時の危険性や狙われる意外なもの、具体的な対策について解説します。
玄関や窓の防犯強化、地域との連携、ホームセキュリティサービスの活用など、高齢者の方々が安心して生活を送るための情報が満載です。
 警童 ひかり
警童 ひかり一人暮らしで不安だけど、何をすればいいのかしら…



まずは現状を把握し、何が必要かを知ることが大切です。
この記事でわかること
この記事でわかること
- 防犯対策の必要性と在宅時の危険性
- 玄関・窓の防犯強化策
- 地域との連携による防犯力アップ
- 安全・安心な暮らしをサポートするサービス
高齢者の一人暮らし、安心のために
この見出しのポイント
高齢者の一人暮らしでは、防犯対策が非常に重要です。
侵入犯は留守中だけでなく、在宅時も高齢者を狙うからです。
この章では、防犯対策の必要性と在宅時の危険性、そして狙われる意外なものを解説します。
これらの情報を知ることで、具体的な対策を講じることができます。
なぜ今、防犯対策が必要なのか
高齢者の一人暮らしが増加しており、侵入犯が高齢者を狙うケースが増えているため、防犯対策は不可欠です。
警察庁のデータによると、在宅中に侵入するケースが3割を超えており、高齢者を狙った悪質な手口も巧妙化しています。
高齢者世帯を狙った犯罪は後を絶たず、深刻な社会問題となっています。



一人暮らしで不安だけど、何をすればいいのかしら…



まずは現状を把握し、何が必要かを知ることが大切です。
留守中だけじゃない、在宅時の危険性
多くの人が留守中の空き巣を警戒しますが、在宅時も侵入犯による被害に遭う可能性があるので注意が必要です。
警察庁の統計によると、住人が在宅中に侵入するケースは3割を超えています。
これは、在宅時であっても油断できないことを示唆しています。
在宅中に侵入された場合、金品を盗まれるだけでなく、身体的な危険にさらされる可能性もあります。
| 侵入場所 | 割合 |
|---|---|
| 一戸建て住宅 | 約50% |
| 共同住宅(3階以下) | 約30% |
| 共同住宅(4階以上) | 約20% |
在宅時にインターホンが鳴った際には、相手をよく確認し、不審な場合はドアを開けないようにしましょう。
現金だけじゃない、狙われる意外なもの
侵入犯が狙うのは、現金や貴金属だけではありません。
預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、ノートパソコン、家電製品、食料品、自転車、バイクなど、あらゆるものがターゲットになり得ます。
「うちには高価なものなどないから、盗まれるものなどない」と考えるのは危険です。
泥棒は換金しやすいものだけでなく、生活に必要なものまで盗んでいきます。
特に高齢者の場合、年金手帳や保険証などを盗まれると、生活に大きな支障をきたす可能性があります。
| 狙われるもの | 具体例 |
|---|---|
| 金銭 | 現金、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード |
| 貴重品 | 貴金属、ブランド品 |
| 家電製品 | ノートパソコン、スマートフォン、テレビ |
| その他 | 食料品、自転車、バイク、年金手帳、保険証 |
高齢者宅は、比較的高級な品が置いてある可能性が高いと考える犯罪者もいます。
侵入犯から身を守る具体的な対策
この見出しのポイント
高齢者の安全を守るためには、侵入犯の視点に立ち、家の弱点を強化することが不可欠です。
玄関、窓といった侵入経路となりやすい場所への対策はもちろんのこと、地域社会との連携もまた、防犯性を高める上で重要な要素となります。
ここでは、具体的な対策について見ていきましょう。
玄関の防犯強化策では補助錠の設置やスマートロックの導入を、窓の防犯強化策では防犯フィルムの有効性や防犯砂利の活用について強調して解説します。
また、地域との連携によって、より強固な防犯体制を構築できることを説明します。
玄関の防犯強化策
玄関は、侵入犯が最も侵入しやすい場所の一つであり、対策を講じることは非常に重要です。
ピッキングやサムターン回しといった手口から玄関を守るために、複数の対策を組み合わせることが効果的です。
例えば、鍵を2つ以上設置したり、防犯性の高い鍵に交換したりすることで、侵入にかかる時間を大幅に増加させることが可能です。
補助錠の設置とその効果
補助錠とは、既存の鍵に追加して取り付ける鍵のことで、侵入犯が鍵を破るのにかかる時間を稼ぎ、侵入を困難にする効果があります。
補助錠を設置することで、仮に一つの鍵が破られたとしても、もう一つの鍵が侵入を防ぐ壁となります。



補助錠ってどんな種類があるんだろう?



補助錠には、さまざまな種類があり、用途や予算に合わせて選ぶことができます
スマートロック導入の検討
スマートロックとは、スマートフォンやカード、暗証番号などを使用して鍵の開閉を行うことができる電子錠のことです。
スマートロックは、鍵を持ち歩く必要がないだけでなく、ピッキング対策としても有効です。
また、遠隔操作で鍵の開閉ができるため、家族の帰宅時に鍵を開けてあげたり、鍵の閉め忘れを防いだりすることも可能です。
窓の防犯強化策
窓は、玄関に次いで侵入犯が侵入しやすい場所であり、特に戸建て住宅の1階や、マンションの低層階にある窓は注意が必要です。
窓ガラスを割って侵入する手口に対しては、防犯フィルムや面格子、二重窓などが有効な対策となります。
防犯フィルムの有効性
防犯フィルムとは、窓ガラスに貼り付けることで、ガラスの強度を高め、割れにくくするフィルムのことです。
防犯フィルムを貼ることで、侵入犯が窓ガラスを割って侵入するのに時間がかかるため、侵入を諦めさせることができます。
| フィルムの種類 | 効果 |
|---|---|
| 透明タイプ | 窓の外観を損なわずに、ガラスの強度を向上させる |
| ミラータイプ | 外からの視線を遮り、プライバシーを保護する |
| UVカットタイプ | 紫外線による家具や畳の日焼けを防止する |
| 防災タイプ | 地震などの災害でガラスが割れた際に、破片の飛散を防止する |



防犯フィルムって自分で貼れるのかな?



自分で貼ることも可能ですが、気泡が入ったり、剥がれたりする可能性があるため、専門業者に依頼するのがおすすめです
防犯砂利で足音をシャットアウト
防犯砂利とは、歩くと大きな音が出るように設計された砂利のことです。
庭や通路に防犯砂利を敷き詰めることで、侵入者が足を踏み入れた際に音が出て、周囲に異変を知らせることができます。
地域との連携で防犯力アップ
防犯対策は、個人の努力だけでは限界があり、地域住民との連携が不可欠です。
近隣住民同士が協力し、地域全体で防犯意識を高めることで、犯罪の抑止につながります。
近隣住民との協力体制
近隣住民と協力し、お互いの家を見守り合う体制を構築することは、防犯対策として非常に有効です。
例えば、留守中に不審な人物がいないか注意したり、異変に気づいたらすぐに連絡を取り合ったりすることで、犯罪を未然に防ぐことができます。
| 協力体制の内容 | 具体例 |
|---|---|
| 声かけ運動 | 地域住民同士が挨拶を交わし、顔見知りになる |
| 見守り活動 | 高齢者や子供の見守り、留守宅への声かけなど |
| 防犯情報の共有 | 地域で発生した犯罪情報や不審者情報を共有する |
| 防犯パトロールへの参加 | 地域住民が交代で地域を巡回し、犯罪抑止活動を行う |



近所付き合いが苦手だけど、何かできることはあるかな?



自治体や町内会が主催する防犯活動に参加したり、地域の防犯情報を共有するだけでも、地域全体の防犯力向上に貢献できます
防犯パトロールへの参加
防犯パトロールとは、地域住民が自主的に行う防犯活動の一つで、地域を巡回し、犯罪の抑止や早期発見に努めます。
防犯パトロールに参加することで、地域の安全を守るだけでなく、住民同士の交流を深めることができます。
安全・安心な暮らしをサポートするサービス
この見出しのポイント
安全・安心な暮らしをサポートするサービスは、高齢者の方々が安心して生活を送る上で非常に重要です。
特に、ALSOK・SECOMといったホームセキュリティサービスや、地域の見守りサービスは、その代表例と言えるでしょう。
これらのサービスを活用することで、万が一の事態に備え、安全な生活を送ることが可能です。
ALSOK・SECOMといったホームセキュリティ
ALSOK(アルソック)やSECOM(セコム)のようなホームセキュリティサービスは、24時間365日体制で住居の安全を監視し、異常時には迅速に対応するシステムです。
侵入者への対策はもちろんのこと、火災や急病など、様々な緊急事態に対応できる点が大きな特徴です。
サービス内容と料金の比較
ホームセキュリティの導入を検討する際、



どんなサービスがあって、料金はどれくらいなんだろう?



各社のサービス内容や料金体系を比較検討することで、最適なプランを見つけられます。
| 項目 | ALSOK | SECOM |
|---|---|---|
| サービス内容 | 24時間遠隔監視、非常通報、緊急対処員派遣、火災監視、救急通報 | 24時間遠隔監視、非常通報、緊急対処員派遣、火災監視、救急通報 |
| 初期費用 | 数万円程度(プランによる) | 数万円程度(プランによる) |
| 月額費用 | 数千円~数万円程度(プランによる) | 数千円~数万円程度(プランによる) |
| 特徴 | 独自のAIガードマン技術、豊富なオプションサービス(見守りサービスなど) | 長年の実績と信頼性、多様なニーズに対応するプラン |
| その他 | 防犯カメラ、センサーライト、非常ボタン | 防犯カメラ、センサーライト、非常ボタン |
| セキュリティ機器の種類 | 開閉センサー、人感センサー、火災センサー、非常ボタンなど | 開閉センサー、人感センサー、火災センサー、非常ボタンなど |
| 付帯サービス | 健康相談サービス、生活支援サービス | 健康相談サービス、生活支援サービス |
| 駆けつけ時間 | 平均25分 | 平均25分 |
| その他サービス | 安否確認サービス、緊急医療サービス | 安否確認サービス、緊急医療サービス |
| 契約期間 | 1年契約 | 1年契約 |
| 解約手数料 | 契約期間内の解約は解約金が発生 | 契約期間内の解約は解約金が発生 |
各社のサービス内容や料金体系を比較検討することで、自身に最適なプランを選択することが重要です。
導入事例から学ぶ
実際にホームセキュリティを導入した家庭の事例を参考にすることで、導入後のイメージが明確になります。
たとえば、東京都にお住まいのAさんの事例では、ALSOKのホームセキュリティを導入したことで、留守中の空き巣被害を未然に防ぐことができました。
また、大阪府にお住まいのBさんの事例では、SECOMの火災監視システムが、早期に火災を検知し、大事に至らずに済んだという事例があります。
これらの事例から、ホームセキュリティが日々の安全に大きく貢献することがわかります。
ホームセキュリティの導入は、高齢者の一人暮らしにとって、非常に有効な手段と言えるでしょう。
地域の見守りサービスを活用
地域の見守りサービスは、地域住民やボランティアが中心となり、高齢者の方々の生活をサポートする取り組みです。
日常的な声かけや訪問、安否確認など、様々な形で高齢者の安全を見守ります。
サービス内容と利用方法



地域の見守りサービスって、具体的にどんなことをしてくれるの?



地域の見守りサービスの内容や利用方法を理解することで、より安心してサービスを利用できます。
| 項目 | 内容 | 利用方法 |
|---|---|---|
| サービス内容 | 安否確認、緊急時の対応、生活相談、交流イベントの開催 | 自治体や社会福祉協議会に相談し、利用登録を行う |
| 対象者 | 65歳以上の高齢者、障がい者、その他支援が必要な方 | |
| 費用 | 無料または低額 | |
| 実施主体 | 自治体、社会福祉協議会、NPO法人、ボランティア団体 | |
| 連携機関 | 医療機関、介護事業所、警察署、消防署 | |
| サービス提供者 | 民生委員、ボランティア、地域住民 | |
| サービスの種類 | 定期的な訪問、電話連絡、緊急通報システムの提供、配食サービス、買い物支援、見守りカメラの設置、センサーによる見守り | |
| 利用頻度 | 週1回~毎日 | |
| 申し込み方法 | 各自治体の窓口や地域包括支援センターに問い合わせる | |
| 注意点 | サービス内容や対象者は地域によって異なる | |
| その他 | 地域のイベントや交流会への参加を促すことで、孤立を防ぐ |
地域の見守りサービスは、高齢者の方々が地域社会とのつながりを保ちながら、安心して生活を送る上で欠かせない存在です。
民生委員との連携
民生委員は、地域住民の相談に応じ、福祉サービスや支援を提供するボランティアです。
高齢者の方々にとっては、身近な相談相手として、また、地域社会との橋渡し役として、重要な存在です。
民生委員との連携を強化することで、高齢者の方々は、より安心して地域での生活を送ることができるようになります。
民生委員に日頃から相談しておくことで、万が一の時にもスムーズな支援を受けることができます。
地域の見守りサービスと民生委員の活動を組み合わせることで、高齢者の方々はより安全で安心な生活を送ることができるでしょう。
よくある質問(FAQ)
- 一人暮らしの高齢者が泥棒に狙われやすいのはなぜですか?
-
高齢者の一人暮らしは、狙われやすい状況を作りやすいからです。特に、留守にしている時間が長かったり、在宅時間が不規則だったりすると、泥棒に侵入の機会を与えてしまう可能性があります。
- 泥棒はどのような物を盗んでいきますか?
-
泥棒が現金や貴金属を盗むことはもちろんですが、それ以外にも預金通帳やキャッシュカード、家電製品、食料品、自転車など、換金しやすいものや生活に必要なものまで幅広く盗んでいきます。
- 玄関の防犯対策として、どのような方法がありますか?
-
玄関の防犯対策としては、補助錠の設置やスマートロックの導入が効果的です。補助錠は、既存の鍵に追加して取り付けることで、侵入者が鍵を破るのにかかる時間を稼ぎます。スマートロックは、鍵を持ち歩く必要がなく、ピッキング対策としても有効です。
- 窓の防犯対策として、どのような方法がありますか?
-
窓の防犯対策としては、防犯フィルムの貼り付けが有効です。防犯フィルムは、窓ガラスの強度を高め、割れにくくする効果があります。また、防犯砂利を庭に敷くことで、侵入者が足を踏み入れた際に音が出て、周囲に異変を知らせることができます。
- 地域との連携で、どのような防犯対策ができますか?
-
近隣住民と協力し、お互いの家を見守り合う体制を構築することで、防犯対策として非常に有効です。留守中に不審な人物がいないか注意したり、異変に気づいたらすぐに連絡を取り合ったりすることで、犯罪を未然に防ぐことができます。
- ホームセキュリティサービスは、どのような場合に役立ちますか?
-
ALSOKやSECOMなどのホームセキュリティサービスは、24時間365日体制で住居の安全を監視し、異常時には迅速に対応するシステムです。侵入者への対策はもちろんのこと、火災や急病など、様々な緊急事態に対応できる点が大きな特徴です。
まとめ
この記事では、高齢者の一人暮らしにおける防犯対策の重要性と具体的な方法について解説します。
この記事のポイント
- 防犯対策の必要性と在宅時の危険性
- 玄関と窓の防犯強化策
- 地域との連携による防犯力向上
この記事を参考に、ご自身の状況に合わせた防犯対策を実践し、安全で安心な生活を送りましょう。