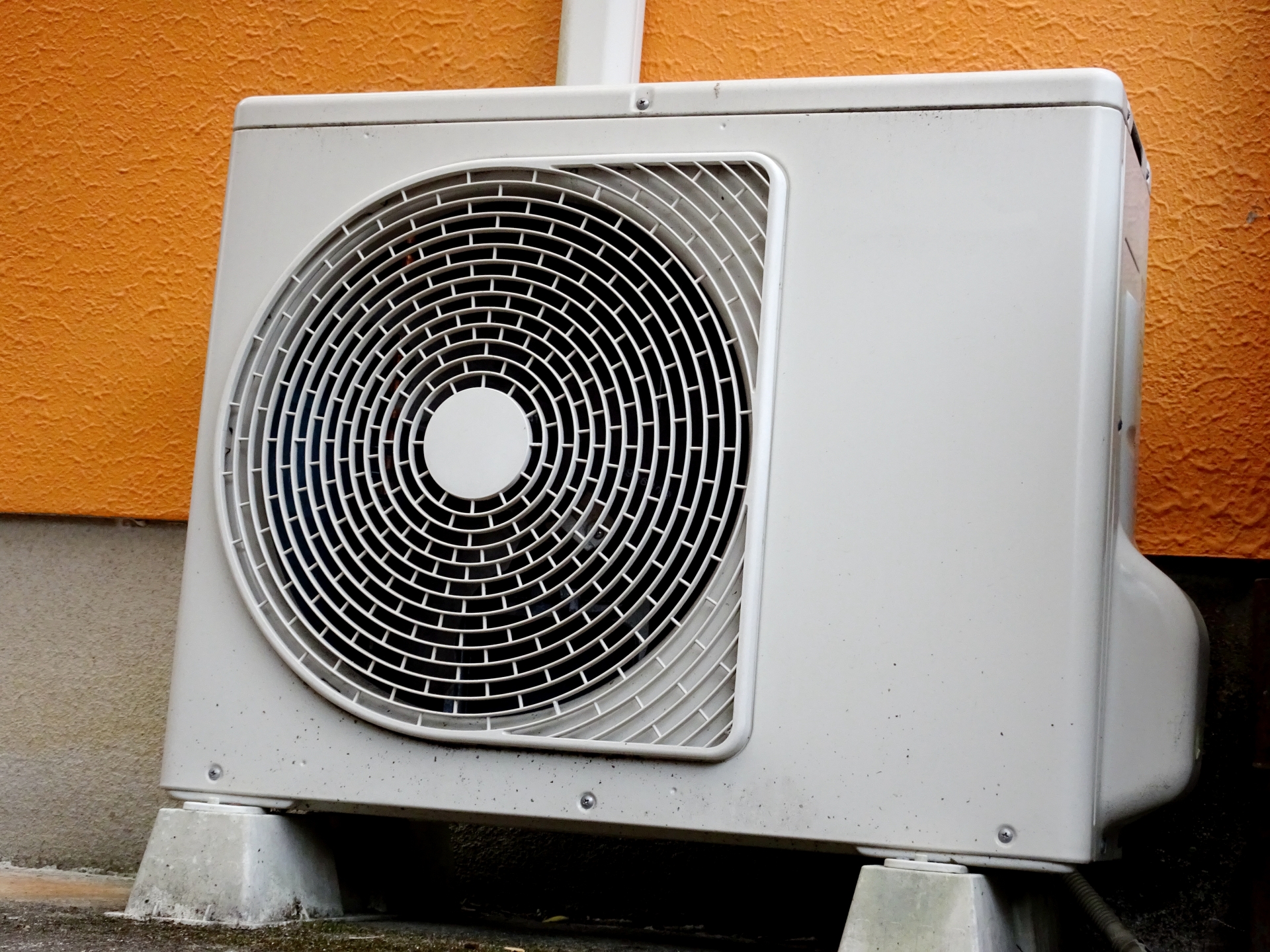共働きのご家庭にとって、お子さんの留守番は日常的な光景ですが、万全な防犯対策が不可欠です。
この記事では、窓や玄関の防犯対策から、緊急連絡先リストの作成、ALSOK/SECOMの活用術まで、具体的な方法をご紹介します。
最後まで読めば、お子様が安心して留守番できる環境を整えられます。
 警童 ひかり
警童 ひかりうちの子、ちゃんと留守番中に戸締りできるかしら…



ALSOKやSECOMなどのホームセキュリティを導入すれば、外出先からでも自宅の状況を確認できて安心ですよ。
この記事でわかること
この記事でわかること
- 窓やドアの防犯強化策
- 防犯グッズの活用術
- 緊急連絡先リストの作成
- ホームセキュリティの検討
子どもの留守番における防犯対策の重要性
この見出しのポイント
共働きのご家庭にとって、お子さんの留守番は日常的な光景です。
しかし、留守番中のお子さんを犯罪や事故から守るためには、万全な防犯対策が不可欠です。
ここでは、共働き家庭が抱える悩みや留守番中のリスク、そして親御さんの不安を軽減するための対策について見ていきましょう。
各ご家庭の状況に合わせて、最適な防犯対策を検討する際の参考にしてください。
共働き家庭の悩み
共働き家庭では、親御さんが仕事で不在の間、お子さんが一人で留守番をすることがあります。
しかし、親御さんにとって、留守番中のお子さんの安全は常に気がかりな問題です。
防犯対策を怠ると、空き巣や不審者の侵入、事故やケガなど、さまざまなリスクにさらされる可能性があります。
| 悩み | 内容 |
|---|---|
| 子どもの安全確保 | 留守番中に、子どもが犯罪や事故に巻き込まれるのではないかという不安 |
| 防犯対策の知識不足 | どのような対策をすれば効果的なのか、具体的な方法がわからない |
| 防犯グッズの選び方 | たくさんの種類がある防犯グッズの中から、どれを選べば良いのか迷ってしまう |
| ホームセキュリティの導入費用 | ホームセキュリティを導入したいが、費用が高くてなかなか手が出せない |
| 近所付き合いの希薄化 | 近隣住民との交流が少ないため、何かあった時に助けを求めにくい |
| 仕事と育児の両立の難しさ | 仕事で忙しい中、防犯対策に時間を割くのが難しい |



仕事で急な残業が入ってしまった。娘が一人で留守番することになるけど、ちゃんと戸締りできるかな…



ALSOKやSECOMなどのホームセキュリティを導入すれば、外出先からでも自宅の状況を確認できて安心ですよ。
共働き家庭では、仕事と育児の両立で時間や心の余裕がなくなりがちです。
そのため、手軽にできる防犯対策や、専門家によるサポートが求められています。
留守番中のリスク理解
留守番中のお子さんは、さまざまなリスクにさらされる可能性があります。
空き巣や不審者の侵入だけでなく、火災や地震などの災害も想定しておく必要があります。
具体的なリスクを理解し、適切な対策を講じることで、お子さんの安全を守りましょう。
| リスク | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 留守中に空き巣が侵入し、金品を盗まれる | 窓やドアの施錠を徹底する。防犯グッズやホームセキュリティを導入する。 |
| 不審者の侵入 | 留守中に不審者が侵入し、子どもに危害を加える | インターホンには出ない、ドアを開けないなどのルールを徹底する。防犯ブザーを持たせる。 |
| 火災 | 調理中や暖房器具の使用中に火災が発生する | 火の元に注意する。火災報知器を設置する。避難経路を確認しておく。 |
| 地震 | 地震が発生し、家具の転倒や落下物によるケガをする | 家具を固定する。落下物を置かない。安全な場所に避難する練習をする。 |
| 交通事故 | 外出中に交通事故に遭う | 交通ルールを守る。危険な場所を通らない。 |
| インターネット上のトラブル | インターネットやSNSで、個人情報を公開したり、犯罪に巻き込まれたりする | インターネットの利用ルールを決め、保護者が見守る。フィルタリングソフトを導入する。 |
| 誘拐 | 外出中に誘拐される | 知らない人に声をかけられてもついて行かない、助けを求める練習をする。 |
小学3年生の娘を持つCさんは、留守番中に不審者がインターホンを鳴らしてドアを開けようとした事例を知り、ALSOKのホームセキュリティを導入しました。
Cさんは「初期費用はかかるけど、子どもの安全には代えられない」と話していました。
親の不安軽減策
留守番中のお子さんの安全を守るためには、親御さんが不安を抱えたまま過ごすのではなく、具体的な対策を講じることで、少しでも不安を軽減することが大切です。
防犯グッズの活用やホームセキュリティの導入、近隣住民との連携など、さまざまな方法を検討してみましょう。
| 対策 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 防犯グッズの活用 | 防犯ブザー、防犯カメラ、窓用補助錠などを活用する | 空き巣や不審者の侵入を抑止する。緊急時に助けを呼べる。 |
| ホームセキュリティの導入 | ALSOKやSECOMなどのホームセキュリティを導入する | 24時間365日の監視体制で、万が一の事態にも迅速に対応してくれる。 |
| 近隣住民との連携 | 近所の人に留守番中の子どもを見守ってもらう | いざという時に助けを求めやすい。 |
| 緊急連絡先リストの作成 | 警察、消防署、親戚などの緊急連絡先をリスト化し、子どもの手の届く場所に置いておく | 緊急時に迅速に連絡できる。 |
| 留守番中のルール策定 | 留守番中の過ごし方、インターホンの対応、火の元など、ルールを決め、子どもと共有する | 子どもの安全意識を高める。 |
| キッズケータイ・見守りサービスの活用 | GPS機能付きのキッズケータイや見守りサービスを活用する | 子どもの現在地を把握できる。緊急時に連絡を取りやすい。 |



一人で留守番させるのは心配だけど、何かあった時にすぐに連絡できる方法はないかな…



キッズケータイや見守りサービスを導入すれば、GPS機能で子どもの居場所を確認できますし、緊急時にはすぐに連絡を取れますよ。
防犯対策は、親御さんの不安を軽減するだけでなく、お子さん自身の安全意識を高める効果もあります。
家族みんなで防犯について話し合い、安心して留守番できる環境を整えましょう。
留守番中の子どもを守る具体的防犯対策
共働きのご家庭にとって、留守番中のお子さまの安全を守ることは非常に重要な課題です。
この章では、窓やドアの防犯対策から、緊急時の連絡先リストの作成まで、具体的な防犯対策をご紹介します。
各対策を参考に、お子さまが安心して留守番できる環境を整えていきましょう。
窓やドアの防犯強化策
留守中の侵入経路として多いのが、窓やドアからの侵入です。
窓やドアの防犯対策を強化することで、空き巣などの侵入を未然に防ぐことが重要になります。
窓やドアの防犯対策を強化することは、お子さまの安全を守る上で不可欠です。
| 対策 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 二重ロック | ドアに二つ以上の鍵を取り付ける | ピッキング対策、侵入に時間がかかるため、抑止効果が期待できる |
| 補助錠 | 窓やドアに追加の鍵を取り付ける | 侵入に時間がかかるため、抑止効果が期待できる |
| 防犯フィルム | 窓ガラスに特殊なフィルムを貼る | ガラスを割れにくくし、侵入を防ぐ |
| 防犯センサー | 窓やドアの開閉を感知して、アラームを鳴らす | 侵入者を威嚇し、近隣に異常を知らせる |
| 面格子 | 窓の外側に格子を取り付ける | 物理的に侵入を防ぐ |
| ドアチェーン | ドアを開ける際に、チェーンでロックする | ドアを少しだけ開けて、相手を確認できる |
| ドアスコープ | ドアに設置された覗き穴 | ドアを開けずに外の様子を確認できる |
| 割れにくいガラス | 防犯ガラスや合わせガラスを使用する | ガラスを割って侵入する手口を防ぐ |
| スマートロック | スマートフォンで鍵の開閉ができる | 鍵の閉め忘れを防止できる、遠隔操作で施錠できる |
| ビデオドアホン | ドアホンにカメラが付いている | 訪問者の顔を確認できる、録画機能付きもある |



窓の鍵が一つしかないけど、本当に大丈夫かな?



二重ロックや補助錠を取り付けることで、防犯性を高められますよ!
窓やドアの防犯対策を徹底し、安全な留守番環境を構築しましょう。
防犯グッズの活用術
防犯グッズは、お子さま自身が身を守るための重要なツールです。
防犯ブザーや非常用ライトなど、用途に合わせたグッズを活用することで、より安全な留守番を実現できます。
適切な防犯グッズの選択と使用方法の理解は、お子さまの安全確保に不可欠です。
| 防犯グッズ | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 防犯ブザー | 危険を感じた時に鳴らす | 周囲に助けを求められる、不審者を威嚇できる |
| 非常用ライト | 停電時や夜間に使用する | 足元を照らし、安全を確保できる |
| 窓用防犯アラーム | 窓の開閉を感知してアラームを鳴らす | 侵入者を威嚇し、近隣に異常を知らせる |
| ドア用防犯アラーム | ドアの開閉を感知してアラームを鳴らす | 侵入者を威嚇し、近隣に異常を知らせる |
| 防犯ステッカー | 防犯対策をしていることをアピールする | 犯罪抑止効果が期待できる |
| 室内用監視カメラ | 留守中の室内を遠隔で確認する | 子どもの様子を確認できる、不審者の侵入を記録できる |
| センサーライト | 人の動きを感知して自動で点灯する | 不審者を威嚇できる、夜間の安全性を高める |
| ダミーカメラ | 本物の防犯カメラと区別がつかないように作られた模倣品 | 犯罪抑止効果が期待できる |
| 防犯砂利 | 歩くと音が鳴る砂利 | 不審者の侵入を音で知らせる |
| 催涙スプレー | 不審者に向けて噴射する | 護身用として使用できる |
これらの防犯グッズを効果的に活用し、お子さまの安全を守りましょう。
緊急連絡先リストの作成
緊急時には、迅速な連絡が不可欠です。
警察、消防、病院、親族など、連絡先をまとめたリストを作成し、お子さまがすぐにアクセスできるようにしておくことが大切です。
緊急連絡先リストは、お子さまが安心して留守番するための重要な備えとなります。
- 警察: 110番
- 消防: 119番
- 救急: 119番
- 医療機関: かかりつけの病院、救急病院
- 親: 勤務先、携帯電話番号
- 親戚: 祖父母、叔父叔母
- 近所の人: 信頼できる近隣住民
- ALSOK/SECOM: ホームセキュリティサービス



緊急連絡先って、たくさんあって覚えられないよ…



リストを作成して、目の届く場所に置いておくと安心ですよ!
緊急連絡先リストを作成し、お子さまがいつでも連絡できるように備えましょう。
留守番中のルール策定
留守番中のルールを明確にすることは、お子さまの安全意識を高める上で重要です。
来客対応、電話対応、外出の禁止など、具体的なルールを決め、親子で共有することで、不測の事態への対応力を高めることができます。
ルール策定は、お子さまが安全に留守番するための基盤となります。
- 来客対応: ドアを開けない、インターホンに出ない
- 電話対応: 知らない電話には出ない、留守番電話に設定する
- 外出の禁止: 許可なく外に出ない
- 火の扱い: 火を使わない、火災に注意する
- インターネット・ゲーム: 使用時間や内容を決める
- 食事: 自分で用意できるものにする、火を使わない
- 友人との連絡: 緊急時以外は控える
- 戸締り: 常に鍵をかける
- 体調不良: 無理せず親に連絡する
- 不審者対応: 大声で助けを求める、防犯ブザーを鳴らす
留守番中のルールを明確にし、お子さまと共有することで、安全な留守番をサポートしましょう。
近隣住民との連携
近隣住民との連携は、地域全体で子どもたちを守るために重要です。
留守番中の子どもに声をかけてもらう、不審な人物を見かけたら連絡してもらうなど、協力体制を築くことで、より安全な環境を作ることができます。
日頃から近隣住民との良好な関係を築き、いざという時に助け合えるようにしておくことが大切です。
- 挨拶を交わす: 日常的なコミュニケーションを心掛ける
- 留守番を伝える: 留守にする時間帯や連絡先を伝えておく
- 協力をお願いする: 子どもの見守りや緊急時の対応を依頼する
- 情報交換をする: 地域の防犯情報や不審者情報を共有する
- 子どもを紹介する: 顔見知りになることで、声かけや見守りがしやすくなる
- 緊急連絡先を交換する: いざという時に連絡を取り合えるようにする
- 防犯活動に参加する: 地域で行われる防犯パトロールなどに参加する
- イベントに誘う: 親睦を深める機会を設ける
- 感謝の気持ちを伝える: 協力してもらった際には、お礼を伝える
- プライバシーに配慮する: 個人情報をむやみに公開しない
近隣住民との連携を強化し、地域全体で子どもたちの安全を守りましょう。
ALSOK/SECOMなどのホームセキュリティ検討
ALSOKやSECOMなどのホームセキュリティは、24時間365日の監視体制で、ご家庭の安全をサポートします。
不審者の侵入を感知すると、警備員が駆けつけ、必要に応じて警察や消防に通報します。
ホームセキュリティの導入は、お子さまだけでなく、家族全体の安心につながります。
| サービス | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ALSOK | 24時間365日の監視、緊急時の駆けつけ、火災監視、非常通報 | 不審者の侵入に対応、火災や急病時にも安心、高齢者や子どもの見守りにも活用できる | 費用がかかる、誤報が多い場合がある、プライバシーへの配慮が必要 |
| SECOM | 24時間365日の監視、緊急時の駆けつけ、医療相談、安否確認 | 不審者の侵入に対応、医療相談や安否確認サービスも利用できる、ALSOKと同様に高齢者や子どもの見守りにも活用できる | 費用がかかる、誤報が多い場合がある、プライバシーへの配慮が必要 |
| 防犯カメラ | 留守中の映像を録画、スマートフォンで確認 | 不審者の侵入を記録できる、子どもの様子を確認できる | プライバシーへの配慮が必要、設置場所によっては近隣住民とのトラブルになる可能性もある |
| スマートホーム | 家電製品を遠隔操作、センサーで異常を感知 | 鍵の閉め忘れを防止、火災や水漏れを早期発見できる、外出先から家電製品を操作できる | 費用がかかる、設定が複雑な場合がある、インターネット環境が必要 |
| キッズ見守りGPS | 子どもの居場所をGPSで確認、緊急時にSOSを発信 | 子どもの現在地を把握できる、迷子や誘拐などのリスクを軽減できる | GPSの精度に限界がある、バッテリーの消費が早い、プライバシーへの配慮が必要 |
| みまもりサービス | オペレーターが子どもの相談に対応、緊急時に駆けつけ | 悩みや不安を相談できる、緊急時には駆けつけてくれる | 費用がかかる、オペレーターとの相性がある |
| 防犯アプリ | 防犯情報を配信、緊急時に家族や友人に通知 | 地域の防犯情報を把握できる、緊急時に連絡を取り合える | バッテリーの消費が早い、情報が正確でない場合がある |
| ネットワークカメラ | スマートフォンで室内の様子を確認、双方向通話が可能 | 子どもの様子を確認できる、声をかけて安心させられる | プライバシーへの配慮が必要、ハッキングのリスクがある |
| IPカメラ | インターネット回線を利用して映像を送信、遠隔地から監視 | 高画質で映像を確認できる、遠隔地からでも監視できる | セキュリティ対策が必要、設置場所によってはプライバシーの侵害になる可能性がある |



ホームセキュリティって、本当に必要なのかな?



もしもの時に、プロが駆けつけてくれる安心感は何にも代えがたいですよ!
ALSOK/SECOMなどのホームセキュリティを検討し、ご家庭に最適な安全対策を講じましょう。
子どもの安心・安全な留守番を実現するために
この見出しのポイント
共働きのご家庭にとって、子どもの留守番は避けて通れない道です。
だからこそ、親御さんとしては、お子さんが安心して安全に過ごせるように、万全の対策を講じることが不可欠です。
この記事では、キッズケータイや見守りサービスの活用から、防災グッズの準備まで、具体的な方法を7つご紹介します。
これらの対策を講じることで、お子さんの安全を守り、親御さんの不安を軽減できます。
キッズケータイ・見守りサービスの活用
キッズケータイや見守りサービスは、GPS機能を通じて子どもの居場所を把握できるツールです。
これらのサービスを活用することで、子どもがどこにいるのかを常に把握し、迷子や誘拐などのリスクを減らすことが可能です



キッズケータイって本当に必要なのかな?



キッズケータイは、緊急時の連絡手段としても非常に有効だよ
防犯アプリの利用
防犯アプリは、子どもの安全をサポートする様々な機能を提供します。
例えば、不審者情報や事件情報をリアルタイムで通知したり、緊急時に保護者や警察に連絡したりすることができます
地域安全マップの確認
地域安全マップとは、犯罪発生情報や不審者情報などを地図上にまとめたものです。
これらのマップを確認することで、子どもが通る道や遊ぶ場所の危険箇所を把握し、未然に事故や犯罪を防ぐことができます
警察への相談窓口
警察では、子どもの安全に関する様々な相談を受け付けています。
例えば、不審者情報や犯罪多発地域の情報提供、防犯対策のアドバイスなどを受けることができます
留守番練習の実施
留守番練習は、子どもが実際に一人で留守番をする前に、様々な状況を想定して行うシミュレーションです。
この練習を通じて、子どもは緊急時の対応や危険回避の方法を学ぶことができます
防災グッズ準備と火災対策
災害はいつ起こるか予測できません。
非常食や飲料水、救急セット、懐中電灯など、最低限必要なものをリュックサックにまとめて、子どもでも持ち出せる場所に置いておきましょう
よくある質問(FAQ)
- 子どもが留守番中にインターホンが鳴ったらどうすればいいですか?
-
お子様には、在宅中であっても、知らない人が来た場合はインターホンに出ないように教えてください。モニター付きインターホンの場合は、相手を確認し、知り合いであれば対応しても大丈夫ですが、念のため親御さんに連絡するように伝えてください。
- 留守番中に地震が起きたら、子どもはどうすればいいですか?
-
まず、机の下など安全な場所に身を隠すように教えてください。揺れが収まったら、火の元を確認し、安全な場所に避難するように伝えてください。事前に避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
- 子どもが留守番中に不審者が来た場合、どうすればいいですか?
-
大声で助けを求め、すぐに防犯ブザーを鳴らすように教えてください。可能であれば、近所の人に助けを求めたり、110番に通報するように伝えてください。
- 留守番中に子どもがケガをしてしまった場合、どうすればいいですか?
-
まず、親御さんに連絡するように教えてください。状況を伝え、指示を仰ぎましょう。必要であれば、救急車を呼ぶことも検討してください。事前に緊急連絡先をまとめたリストを用意しておくと安心です。
- 留守番中に火災が発生した場合、子どもはどうすればいいですか?
-
大声で「火事だ!」と叫び、すぐに避難するように教えてください。避難経路を確認し、安全な場所に避難してください。避難後は、消防署(119番)に通報しましょう。
- 子どもが留守番中に友達が遊びに来てもいいですか?
-
事前にルールを決めておくことが大切です。基本的には、留守番中は友達を家に呼ばないようにしましょう。どうしても友達と会いたい場合は、親御さんに相談し、許可を得るように伝えてください。
まとめ
この記事では、共働き家庭で子どもが安全に留守番するための防犯対策について解説します。
この記事のポイント
- 窓やドアの二重ロックや防犯フィルムの活用
- 防犯ブザーや室内用監視カメラなどの防犯グッズの使用
- 緊急連絡先リストの作成と共有
これらの対策を参考に、子どもが安心して留守番できる環境を整えましょう。