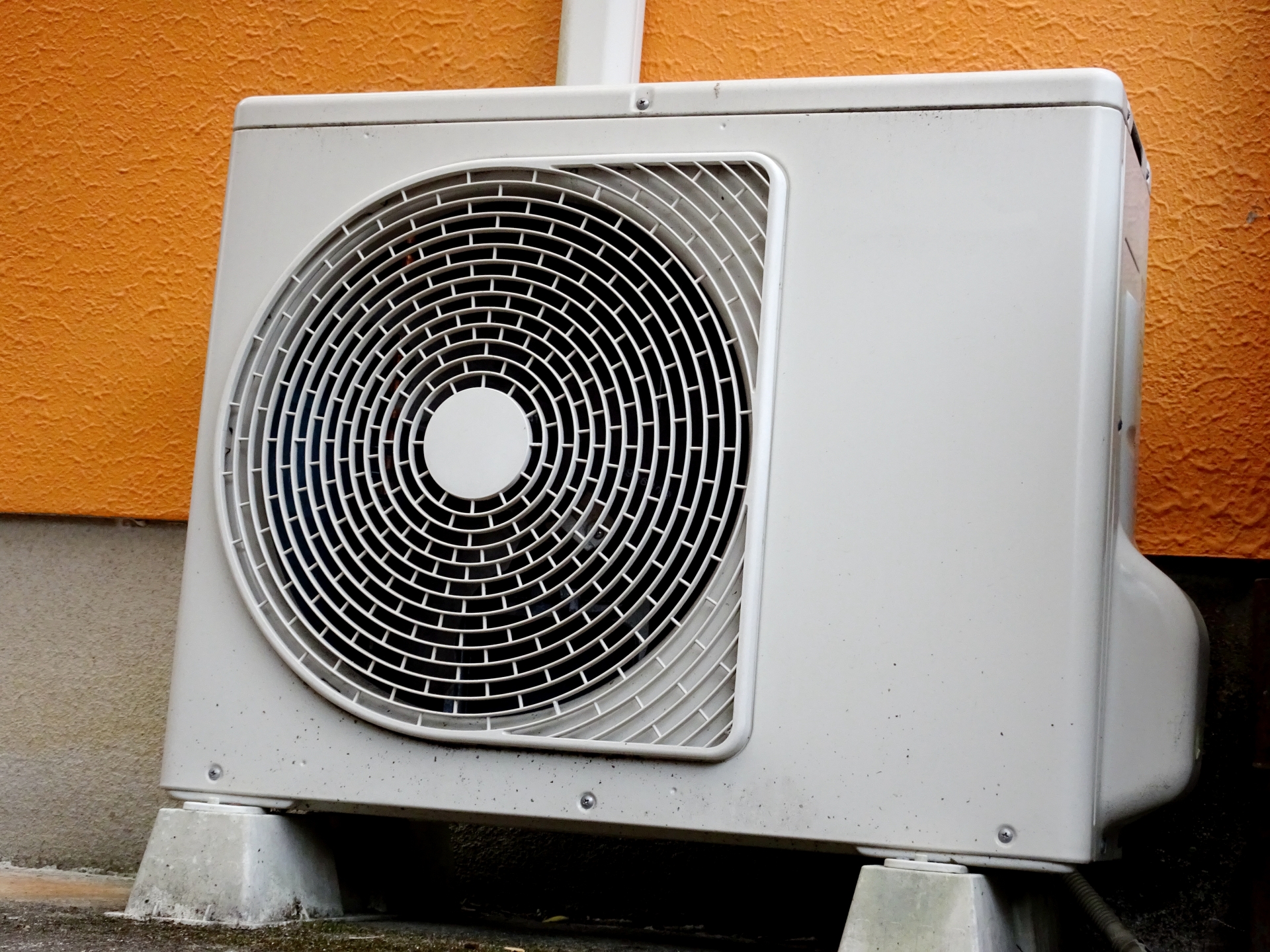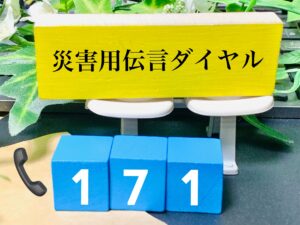突然の車両火災は決して他人事ではありません。
年間3,512件も発生しており、身近なリスクとして備えが必要です。
この記事では、車両火災の7大原因から初期消火、保険適用まで、万が一の事態に役立つ情報を網羅的に解説します。
 警童 ひかり
警童 ひかり自分の車は大丈夫かな…



この記事を読めば、車両火災の原因と対策がわかり、安心して運転できます。
この記事でわかること
- 車両火災の7大原因と予防策
- 火災発生時の初期消火と対処法
- 保険とロードサービスの活用
- 日常点検とメンテナンスのポイント
車両火災の実態と対策の必要性
この見出しのポイント
車両火災は決して他人事ではありません。
万が一の事態に備え、実態を把握し適切な対策を講じることが重要です。
車両火災は、発生件数や事故の背景にある安全意識の重要性からも、その対策の必要性が理解できます。
この記事では、車両火災の実態と対策について解説します。
車両火災は他人事ではない事実
車両火災は決して他人事ではありません。
2021年には全国で3,512件も発生しており、1日あたり約9件の頻度で発生しています。
いつ自分の身に降りかかってもおかしくない事態であることを認識する必要があります



車両火災なんてめったに起こらないんじゃないの?



車両火災は意外と身近な問題です。
車両火災の発生件数と事故の実態
車両火災の発生件数は決して少なくありません。
2021年には全国で3,512件発生しており、71名の方が亡くなっています。
経済的な損害も大きく、21億5,290万円にものぼります
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 発生件数 | 3,512件 |
| 死亡者数 | 71名 |
| 損害額 | 21億5,290万円 |



車両火災で亡くなる人がいるなんて怖い。



車両火災は命に関わる事故であることを認識しましょう。
事故の背景にある安全意識の重要性
車両火災の背景には、安全意識の欠如が潜んでいます。
定期的な点検やメンテナンスを怠ったり、車内に可燃物を放置したりすることが、火災の原因となることがあります。
日頃から安全意識を高め、車両火災を予防することが重要です
車両火災の7大原因と予防策
車両火災の原因を知ることは、事故を未然に防ぐ上で非常に重要です。
車両火災の主な原因と、それぞれの予防策を理解しておきましょう。
ここでは、排気管からの出火や燃料漏れ、電気系統のショートなど、特に注意すべき7つの原因について、具体的な対策を解説します。
車両火災原因1位:排気管からの出火
排気管からの出火は、車両火災の最も多い原因です。
排気管が高温になることで、周囲の可燃物に引火するケースがほとんどです。
定期的な点検で燃料漏れがないかを確認し、可燃物を近づけないように注意する必要があります。



排気管って、具体的にどこに気を付ければいいんだろう?



排気管周辺の清掃と点検を定期的に行うことが重要です。
車両火災原因2位:燃料漏れによる引火
燃料漏れは、非常に危険な車両火災の原因です。
漏れた燃料が、高温になったエンジンや排気管に触れることで引火します。
燃料の臭いがしたり、燃料の減りが早かったりする場合は、すぐに点検してもらいましょう。
車両火災原因3位:電気系統のショート
電気系統のショートは、車両火災の深刻な原因の一つです。
配線の劣化や損傷によりショートが発生し、火花が散って周囲の可燃物に引火することがあります。
定期的な点検で配線の状態を確認し、異常があれば早めに修理することが大切です。



古い車に乗っているんだけど、電気系統は特に注意が必要?



古い車ほど配線が劣化しやすいため、電気系統の点検はより重要になります。
車両火災原因4位:エンジンルームの過熱
エンジンルームの過熱も、車両火災の原因となります。
冷却水の不足やラジエーターの故障などが原因で、エンジンが異常に高温になり、周囲の可燃物に引火する可能性があります。
車両火災原因5位:バッテリーの不具合
バッテリーの不具合も、車両火災の原因となり得ます。
バッテリー液の漏れや、ターミナルの緩みなどが原因で、ショートや発熱が発生し、火災につながることがあります。
定期的なバッテリー点検を行いましょう。
車両火災原因6位:車内への可燃物放置
車内に可燃物を放置することも、車両火災の原因になります。
特に夏場は、ライターやスプレー缶などが高温になりやすく、爆発や引火の危険性があります。
車内には可燃物を放置しないようにしましょう。
車両火災原因7位:放火やいたずら
放火やいたずらも、車両火災の原因の一つです。
駐車場や人気のない場所に駐車している場合、放火の標的にされる可能性もあります。
防犯カメラの設置や、明るい場所に駐車するなどの対策が必要です。
車両火災を防ぐためには、日頃の点検と注意が欠かせません。
万が一、車両火災が発生した場合は、落ち着いて適切な対処を行いましょう。
車両火災発生時の消火と対処法
車両火災発生時は、初期対応と安全確保が重要です。
初期対応を誤ると、被害が拡大するだけでなく、人命に関わる事態にもなりかねません。
ここでは、車両火災発生時の初期対応から、消火器の種類と選び方、避難方法、消防への連絡まで、一連の流れを解説します。
万が一の事態に遭遇した場合でも、落ち着いて対処できるよう、手順を覚えておきましょう。
車両火災発生時の初期対応手順
車両火災が発生した場合、ハザードランプを点灯させ、安全な場所に速やかに停車することが重要です。
その後、エンジンを停止し、周囲の安全を確認してから、乗員全員を車外へ避難させます。
二次的な事故を防ぐために、後続車への注意喚起も忘れずに行いましょう。



どうすれば安全に停車できるの?



まずは落ち着いて、周囲の状況を確認することが大切です。
消火器の種類と選び方、使用方法
車両火災の初期消火には、消火器が有効です。
消火器には様々な種類がありますが、車両火災には、粉末消火器や強化液消火器が適しています。
使用方法は、消火器に記載されている指示に従い、火元に向けて放射します。
風上から近づき、炎を避けて根元を狙うのがポイントです。
| 消火器の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 粉末消火器 | 広い範囲の火災に対応可能、比較的安価 |
| 強化液消火器 | 油火災に強く、再燃防止効果が高い |
| エアゾール式消火具 | 小型で軽量、初期消火に便利だが、消火能力は低い |
| 住宅用消火器 | 家庭での使用を想定、扱いやすいが、車両火災には不向き |
安全な場所への避難と二次被害防止
初期消火が困難な場合や、炎が拡大している場合は、無理に消火を試みず、安全な場所へ避難することが最優先です。
車両から100m以上離れた場所に避難し、爆発などの二次的な被害に備えましょう。



どこに避難すれば安全なの?



周囲に燃えやすいものがない、開けた場所が安全です。
消防への連絡と状況説明のポイント
避難後、速やかに消防(119番)へ連絡し、火災の発生場所、車種、状況などを正確に伝えます。
消防隊の到着を待ち、指示に従って行動しましょう。
また、可能であれば、周囲の交通整理や、消防隊への情報提供など、協力できる範囲で支援を行うことも重要です。
車両火災に備えた保険とロードサービス
この見出しのポイント
車両火災はいつどこで起こるか予測できないからこそ、万が一の事態に備えて保険とロードサービスの加入を検討することが重要です。
ここでは、車両保険、火災保険、ロードサービス、JAFの会員特典について解説します。
それぞれのサービス内容や適用範囲を理解することで、より適切な備えができるようになるでしょう。
車両保険の加入で得られる補償
車両保険とは、自動車事故によって自分の車が損害を受けた場合に、修理費用や買い替え費用を補償する保険です。
火災による損害も補償対象となるため、車両火災で車が燃えてしまった場合にも保険金が支払われます。



車両保険って、火災でも使えるの?



車両保険に加入していれば、火災で車が燃えてしまっても修理費用や買い替え費用が補償されます!
| 補償の種類 | 内容 |
|---|---|
| 車両保険(一般型) | 他車との衝突、自損事故、盗難、火災、台風、いたずらなど、幅広い損害を補償 |
| 車両保険(限定型) | 他車との衝突・接触事故、盗難、火災、台風、いたずらなどを補償(自損事故は対象外) |
車両保険には、一般型と限定型(エコノミー型)があり、補償範囲や保険料が異なります。
一般型は、自損事故や当て逃げなど、幅広い損害を補償する一方、限定型は、補償範囲を限定することで保険料を抑えています。
車両火災に備える場合は、火災が補償対象となる車両保険を選ぶ必要があります。
火災保険の適用範囲と注意点
火災保険は、建物や家財が火災によって損害を受けた場合に、その損害を補償する保険です。
一般的に、自動車は火災保険の対象とはなりませんが、自宅の駐車場に止めていた車が火災に巻き込まれた場合など、例外的に補償されるケースがあります。



火災保険で車の火災も補償されることってあるの?



火災保険は基本的に建物や家財が対象ですが、自宅の駐車場での火災など、例外的に補償される場合があります。
火災保険で自動車が補償されるケース:
- 車庫や駐車場に保管中の自動車が火災に巻き込まれた場合
- 隣家からの延焼で自動車が損害を受けた場合
火災保険で自動車が補償されないケース:
- 自動車自体が原因で火災が発生した場合
- 自動車保険で火災による損害が補償される場合
火災保険で自動車の損害が補償されるかどうかは、保険会社や契約内容によって異なります。
自動車の火災に備える場合は、車両保険への加入を検討するのが一般的です。
ロードサービスの活用方法
ロードサービスは、自動車の故障や事故が発生した際に、現場での応急処置やレッカー移動などのサービスを提供するものです。
車両火災が発生した場合にも、ロードサービスを利用して、安全な場所へのレッカー移動や、最寄りの修理工場への搬送を依頼できます。



ロードサービスって、どんな時に使えるの?



ロードサービスは、故障や事故だけでなく、車両火災の際にもレッカー移動や修理工場への搬送を依頼できます。
ロードサービスで対応可能な主な内容:
| サービス内容 | 詳細 |
|---|---|
| レッカーサービス | 車両火災で走行不能になった車を、安全な場所や修理工場までレッカー移動 |
| 応急処置 | バッテリー上がりやガス欠など、軽微なトラブルに対応 |
| 事故対応 | 事故現場での状況確認や、保険会社への連絡サポート |
ロードサービスは、自動車保険に付帯している場合や、JAFなどの会員制サービスとして提供されている場合があります。
車両火災に備える場合は、ロードサービスの内容を確認し、火災時の対応が含まれているかを確認することが重要です。
JAFの会員特典と車両火災への対応
JAF(日本自動車連盟)は、自動車に関する様々なサービスを提供する会員制の団体です。
JAFの会員になると、ロードサービスや会員特典を利用できます。
JAFのロードサービスは、車両火災にも対応しており、現場での応急処置やレッカー移動などのサービスを提供しています。



JAFって、どんな特典があるの?



JAFの会員になると、ロードサービスだけでなく、様々な会員特典も利用できます!
JAFの会員特典:
| 特典内容 | 詳細 |
|---|---|
| ロードサービス | バッテリー上がり、ガス欠、キー閉じ込め、車両火災などに対応 |
| 会員優待施設割引 | 全国のホテル、レストラン、レジャー施設などで割引や優待サービスが利用可能 |
| JAF Mate | 会員向けの情報誌「JAF Mate」が毎月送付 |
JAFの会員は、車両火災が発生した場合、24時間365日対応のロードサービスを利用できます。
また、JAFの会員特典として、全国の様々な施設で割引や優待サービスが受けられます。
車両火災に備えるだけでなく、日々のカーライフをより快適にするためにも、JAFへの入会を検討してみてはいかがでしょうか。
車両火災を防ぐための点検とメンテナンス
この見出しのポイント
車両火災を防ぐためには、日頃からの点検とメンテナンスが不可欠です。
なぜなら、小さな異常が放置されることで、大きな事故につながる可能性があるからです。
ここでは、日常点検で確認すべきポイント、定期点検の重要性と実施項目、異音や異臭に気づいた際の対処法、そして国土交通省が推奨する安全対策について詳しく解説していきます。
日常点検で確認すべきポイント
日常点検とは、毎日または運転前に車両の状態を簡単に確認することです。
これにより、異常の早期発見につながり、事故を未然に防ぐことができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイヤの空気圧 | 適正な空気圧であるか確認する。不足している場合は補充する |
| タイヤの溝 | 溝の深さが十分であるか確認する。摩耗している場合は交換を検討する |
| エンジンオイル | 量が適正であるか、汚れや漏れがないか確認する。必要に応じて補充または交換する |
| 冷却水 | 量が適正であるか、漏れがないか確認する。不足している場合は補充する |
| バッテリー | 端子の緩みや腐食がないか確認する。異常があれば専門業者に点検を依頼する |
| ランプ類 | ヘッドライト、ブレーキランプ、ウインカーなどが正常に点灯するか確認する。球切れの場合は交換する |
| 異音・異臭 | エンジンルームや車内から異音や異臭がしないか確認する。異常があれば専門業者に点検を依頼する |



毎日確認するのは大変だな



適切な頻度で点検することで、車両火災のリスクを減らすことができます
日常点検を確実に行うことで、車両火災のリスクを大幅に減らすことができるのです。
定期点検の重要性と実施項目
定期点検とは、法律で定められた点検で、プロの整備士による詳細なチェックを受けることです。
これにより、日常点検では見つけられない潜在的な問題を発見し、安全な走行を確保できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エンジン | 圧縮、点火、燃料供給などの状態を点検 |
| ブレーキ | パッドの摩耗、液漏れ、配管の損傷などを点検 |
| サスペンション | ショックアブソーバーの漏れ、スプリングのへたりなどを点検 |
| 電気系統 | バッテリー、配線、ヒューズなどを点検 |
| 排気ガス | CO(一酸化炭素)、HC(炭化水素)などの濃度を測定 |
| 下回り | 車体、マフラー、燃料タンクなどの錆、損傷などを点検 |
| タイヤ | 摩耗状態、亀裂、損傷などを点検 |



定期点検って費用がかかるから、つい後回しにしちゃうんだよね



定期点検は安全のためだけでなく、結果的に修理費用を抑えることにもつながります
定期点検をきちんと実施することで、車両の状態を把握し、安全なカーライフを送ることが可能です。
異音や異臭に気づいた際の対処法
異音や異臭は、車両に何らかの異常が発生しているサインです。
放置せずに適切な対処を行うことで、車両火災などの重大な事故を防ぐことができます。
| 異音・異臭の種類 | 考えられる原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 焦げ臭い | 電気系統のショート、オイル漏れ、ブレーキの異常 | すぐに安全な場所に停車し、原因を特定する。特定できない場合は専門業者に連絡する |
| 異音 | エンジンからの異音:オイル不足、オーバーヒート、部品の破損ブレーキからの異音:パッドの摩耗、ローターの歪み | すぐに安全な場所に停車し、原因を特定する。特定できない場合は専門業者に連絡する |
| 燃料臭い | 燃料漏れ | エンジンを停止し、火気厳禁にする。燃料が漏れている箇所を確認し、専門業者に連絡する |
| 甘い臭い | 冷却水漏れ | エンジンを停止し、冷却水の量を確認する。不足している場合は補充する。漏れが止まらない場合は専門業者に連絡する |



どんな異音や異臭に気を付ければいいの?



いつもと違うと感じたら、迷わず専門業者に相談することが大切です
異音や異臭に気づいたら、早急な対応が車両火災を防ぐ上で非常に重要です。
国土交通省が推奨する安全対策
国土交通省は、車両火災を防止するために、様々な安全対策を推奨しています。
これらの対策を実践することで、車両火災のリスクをさらに低減させることが可能です。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 定期的な点検・整備の実施 | 法令で定められた点検だけでなく、日常点検も行う。プロの整備士による定期的な点検を受ける |
| 適切なメンテナンス | エンジンオイル、冷却水、ブレーキオイルなどの定期的な交換。タイヤの空気圧調整、バッテリーの点検など |
| 車内への可燃物の持ち込み制限 | ライター、スプレー缶、ガソリン携行缶などの可燃物を車内に放置しない。特に夏季は高温になるため注意が必要 |
| 電気配線の点検・修理 | 配線の劣化、損傷、接続不良などを定期的に点検し、必要に応じて修理する。特に古い車両は配線の劣化が進んでいる可能性があるため注意が必要 |
| リコールの確認 | 国土交通省のウェブサイトや自動車メーカーのウェブサイトで、リコール情報を確認する。対象車両の場合は、速やかに修理を受ける |
| 消火器の設置 | 車内に消火器を設置し、使い方を習得しておく。万が一火災が発生した場合に、初期消火に役立つ |



リコールってどんな時に発表されるの?



リコールは、自動車の設計や製造に問題があり、安全基準を満たさない場合に発表されます
国土交通省が推奨する安全対策を実践し、安全なカーライフを送りましょう。
よくある質問(FAQ)
- 車両火災は他人事ですか?
-
2021年には全国で3,512件も発生しており、1日あたり約9件の頻度で発生しているため、決して他人事ではありません。
- 車両火災の原因で最も多いのは何ですか?
-
排気管からの出火が最も多い原因です。燃料漏れや可燃物が接触することで引火するケースが多く見られます。
- 車両火災を予防するために、車内に置いてはいけないものはありますか?
-
ライターやスプレー缶などの可燃物は、特に夏場は高温になりやすく、爆発や引火の危険性があるため、車内に放置しないようにしましょう。
- 車両火災が発生した場合、まず何をすれば良いですか?
-
ハザードランプを点灯させて安全な場所に停車し、119番に通報してください。その後、可能な範囲で初期消火を行い、車から離れて安全な場所に避難してください。
- 車両保険は火災にも適用されますか?
-
車両保険に加入していれば、火災で車が燃えてしまっても修理費用や買い替え費用が補償されます。一般型と限定型がありますが、火災が補償対象となる車両保険を選ぶ必要があります。
- 車両火災を防ぐために、日頃からできることはありますか?
-
日常点検や定期点検を実施し、異音や異臭に気づいたら放置せずに専門業者に相談することが大切です。また、国土交通省が推奨する安全対策を実践しましょう。
まとめ
この記事では、意外と頻繁に発生している車両火災事故の実態とその原因、車両火災の予防法や万一車両火災に立ち会った際の消火方法などをご紹介します。
この記事のポイント
- 車両火災の7大原因と予防策
- 火災発生時の初期消火と対処法
- 保険とロードサービスの活用
- 日常点検とメンテナンスのポイント
万が一の事態に備え、この記事を参考に今すぐ車両の安全点検を実施しましょう。